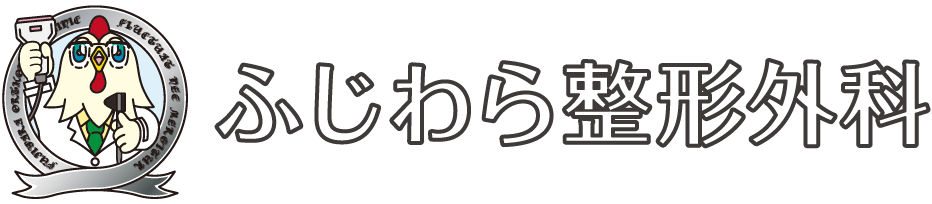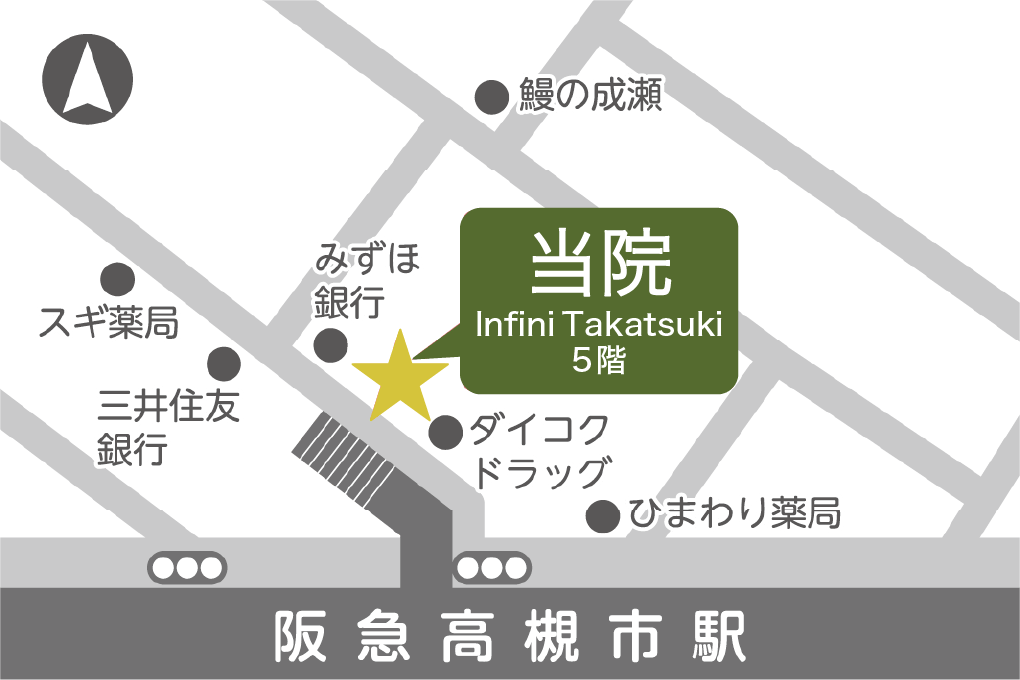骨粗鬆症は骨が構造的に脆くなり
骨折しやすくなる病気です

骨粗鬆症は、骨の密度や強度が低下し、骨折のリスクが高まる病気です。特に高齢者や閉経後の女性に多く見られ、日本では年々患者数が増加しています。骨折は背骨(脊椎)、股関節、手首などに起こりやすく、日常生活に大きな支障をきたす原因となります。とくに高齢者の大腿骨近位部骨折は、
寝たきりや認知機能の低下にもつながるため、早期発見と予防が非常に重要です。
骨粗鬆症は「静かな病気」とも呼ばれ、自覚症状がないまま進行することが多いため、定期的な検査や予防的な治療が欠かせません。50歳以上の方、骨折経験のある方、またご家族に骨粗鬆症の方がいる方は、一度検査を受けてみることをおすすめします。
骨粗鬆症の検査、診断方法
骨粗鬆症の診断において、骨密度を正確に評価することは非常に重要です。一般的に、簡易的な検査として手首や踵(かかと)の骨を用いた測定法が知られていますが、これらの部位は骨粗鬆症による骨折が起こりやすい部位ではありません。そのため、こうした測定方法では、骨折リスクの高い部位の骨の状態を的確に把握することが難しく、十分な評価ができないとされています。
最新のDXA(デキサ)法による骨密度測定装置を導入しています。前腕骨の骨密度を正確に測定することで、骨の状態を科学的に把握し、将来の骨折リスクを予測することが可能です。

骨粗鬆症の治療
-
食事療法
カルシウム、ビタミンD、ビタミンK、たんぱく質などをバランスよく摂取することが大切です。骨の材料となる栄養素を意識して食生活を整えます。
-
運動療法
適度な運動は骨への刺激となり、骨密度の維持・向上に効果があります。ウォーキングや軽い筋力トレーニングがおすすめです。
-
日光浴(ビタミンDの生成)
日光に当たることで体内でビタミンDが合成され、カルシウムの吸収が促進されます。1日15分〜30分程度の散歩が目安です。
-
内服薬による治療
骨の破壊を抑える薬や、骨の形成を促進する薬、ホルモンに作用する薬などがあります。
-
注射薬による治療
月1回や半年に1回の皮下注射、あるいは骨形成促進剤の毎日自己注射など、症状やライフスタイルに応じた選択が可能です。
-
定期的な検査と経過観察
骨密度測定や血液検査を定期的に行い、治療の効果を確認しながら方針を見直していきます。